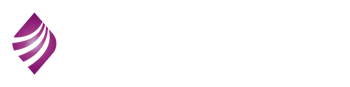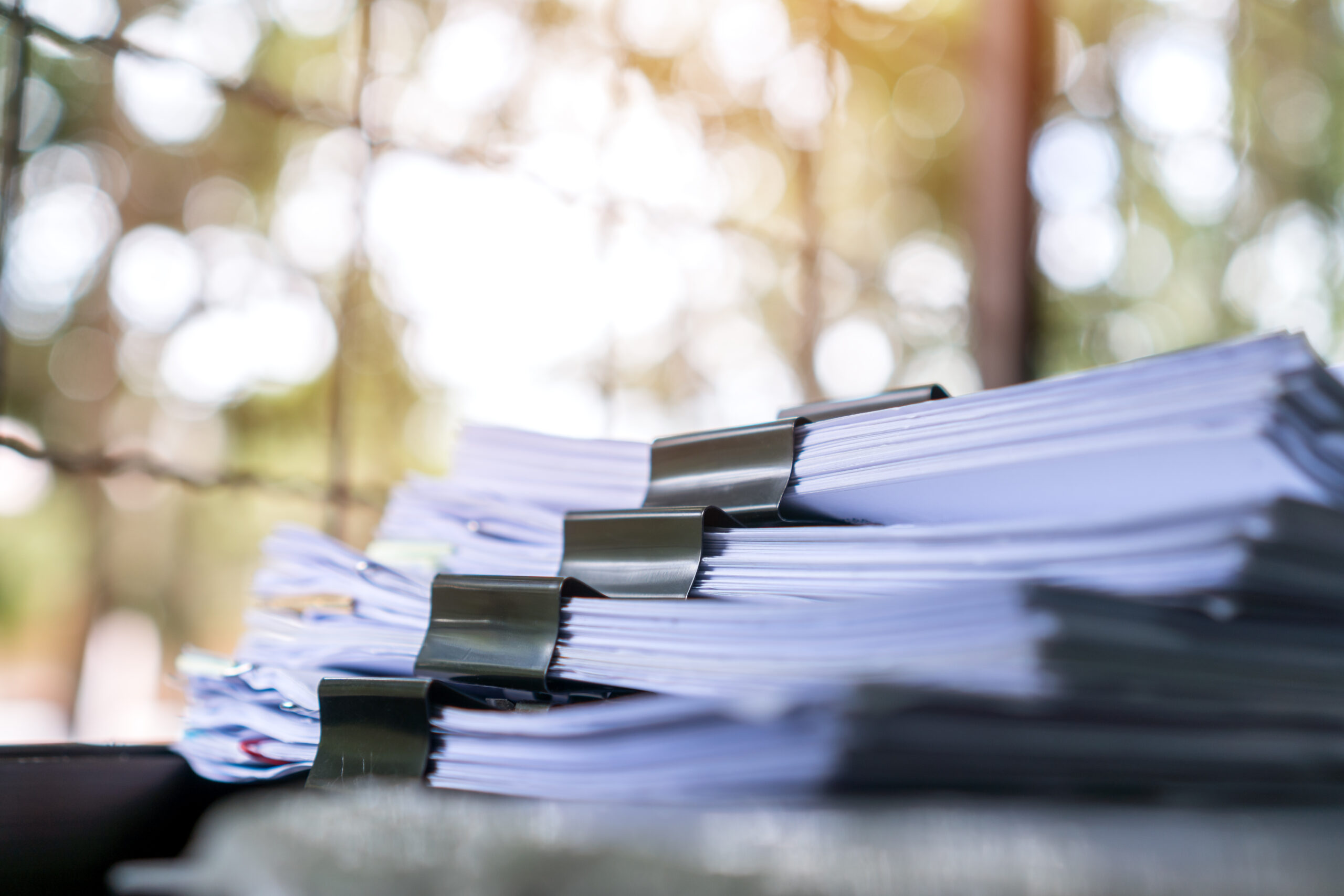労働基準法の40年ぶりの大改正:企業が押さえるべきポイント
2025年に向けて、労働基準法が約40年ぶりに抜本的な改正を迎える見通しです。政府は、労働環境の変化に対応するため、労働者の定義や労働時間制度、労使関係の在り方など、多岐にわたる見直しを進めています。
本記事では、改正の背景と今後想定される改正ポイント、そして企業が取るべき対応についてわかりやすく解説します。
1. 労働基準法改正の背景
近年、テレワークや副業の浸透、非正規雇用の増加といった労働形態の多様化により、昭和的な労働制度では対応が難しくなってきました。
さらに、少子高齢化に伴う労働力不足や、働き方改革の推進なども相まって、現行法の見直しは急務とされています。
2. 改正の主な論点
① 「労働者」の定義見直し
現在の労働者定義は、正社員を基準にしており、個人事業主やフリーランス、ギグワーカーなどが十分に保護されないケースが指摘されています。
今後は「雇用類似の働き方」も一定程度保護対象に含める方向で検討されています。
② 労働時間制度の柔軟化
働き方の多様化に対応するため、裁量労働制やフレックスタイム制の見直しも論点です。
特に「中抜け勤務」や「週単位での労働時間管理」などが導入される可能性もあります。
③ 過半数代表者の選出ルール厳格化
36協定の締結や就業規則の意見聴取に関わる「過半数代表者」の選出方法について、形式的な運用が問題視されています。
今後は、民主的な手続きによる適正な選出が法的に求められる方向です。
④ 労使コミュニケーションの強化
労使間の情報共有や対話の質向上を目的に、「労使協議の記録義務化」や「説明責任の強化」なども検討されています。
3. 企業が押さえるべき実務ポイント
- 社内での「労働者」定義の整理と契約書・就業規則の見直し
- 労働時間の記録・運用方法の見直し(システム対応含む)
- 過半数代表者の選出手続きの厳格化と文書化
- 従業員との対話や説明責任に関する体制整備
4. 今後のスケジュールと対応のすすめ
改正法案は2025年通常国会での提出が見込まれており、施行までには準備期間が設けられる見込みです。
今のうちから現状の運用を棚卸しし、対応が必要な分野を洗い出しておくことが重要です。
5. まとめ
今回の労基法改正は単なる法改正にとどまらず、企業の労務管理体制全体を見直す大きな契機となります。
「知らなかった」「間に合わなかった」では済まされません。社労士や労務コンサルタントと連携し、早めの情報収集と対応を進めていきましょう。
※本記事は2024年12月時点の情報に基づいています。最新情報は厚生労働省等の公式発表をご確認ください。