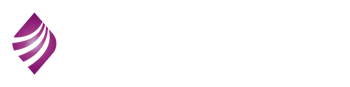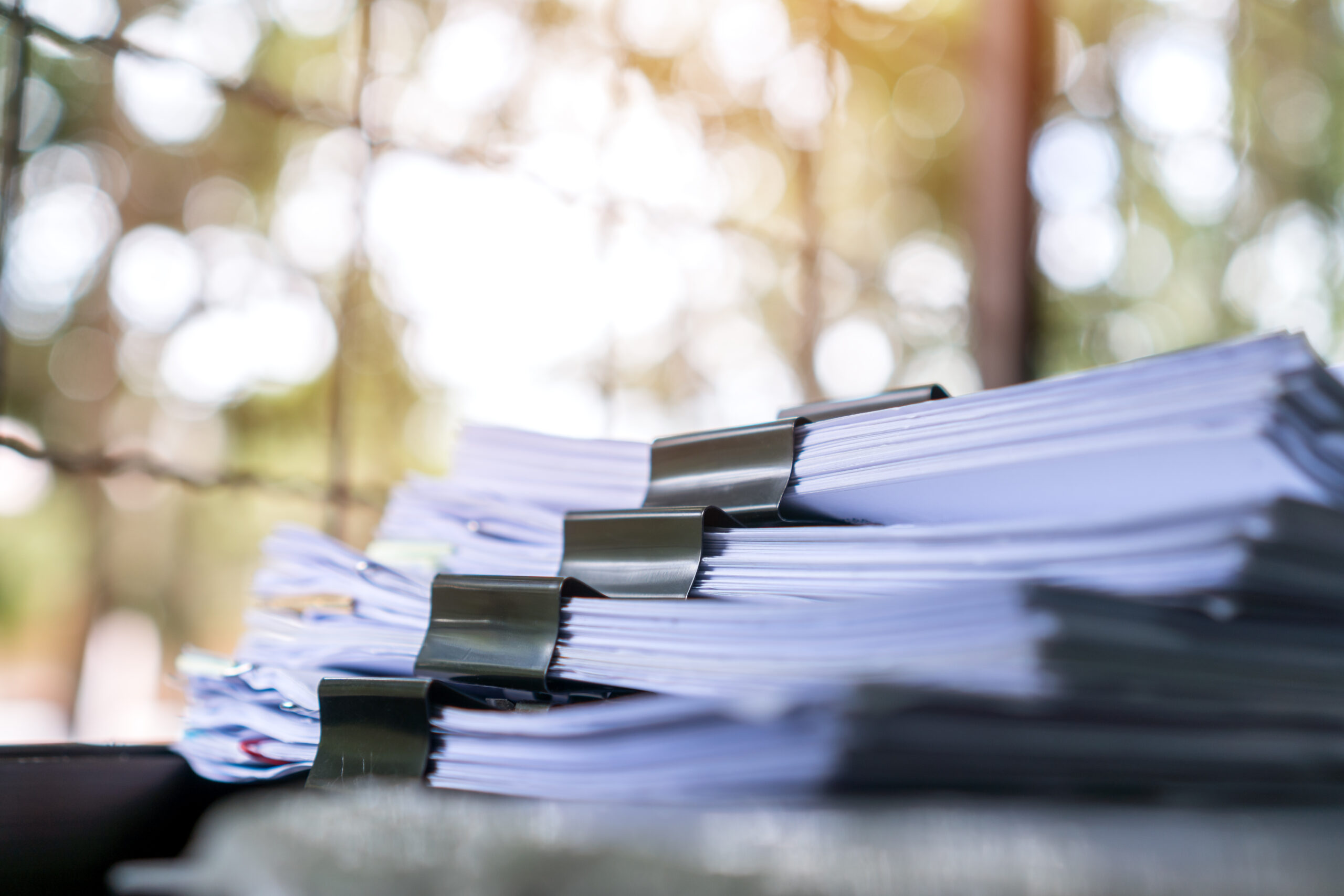副業・兼業の就業規則、見直していますか?厚労省の最新モデル就業規則を読み解く
副業・兼業が当たり前になりつつあるいま、企業の就業規則はそれに対応できていますか?
2024年、厚生労働省の「モデル就業規則」が改訂され、副業・兼業の扱いに関する項目が大幅に見直されました。
本記事では、モデル規則の変更点と、それを踏まえて企業が就業規則をどのように見直すべきかを解説します。
1. なぜ副業・兼業に対応する必要があるのか?
政府は「働き方改革実行計画」の一環として副業・兼業の促進を掲げており、厚労省は“原則容認”の立場を明確にしています。
従業員からの副業申請があったときに、就業規則が旧態依然とした「全面禁止」のままだと、トラブルや訴訟リスクに発展する可能性があります。
2. 厚労省モデル就業規則(2024年改訂)の変更点
2024年の改訂では、副業・兼業に関する条文が次のように整理されました
- 「原則として副業・兼業を認める」という方針に明記
- 企業が制限できる条件(健康支障、秘密漏洩、競業など)を具体化
- 事前の届け出・報告義務を明示
以下のような条文例が推奨されています
労働者は、副業・兼業を行う場合には、会社に届け出なければならない。会社は、次のいずれかに該当すると認めるときは、副業・兼業を制限又は禁止することがある。
- 労働時間が過重となり、労働者の健康が損なわれるおそれがあるとき
- 会社の業務に支障を及ぼすとき
- 会社の信用・名誉を毀損するおそれがあるとき
- 機密情報が漏洩するおそれがあるとき
3. 許可制 or 届出制?実務上の判断ポイント
企業によって、副業制度を「事前許可制」とするか「届出制」とするかは悩ましい問題です。
届出制は柔軟ですが、事後トラブルへの対応が遅れるリスクがあります。
一方、許可制は統制しやすいものの、従業員の反発を招くおそれがあります。
実務では、「原則届出制+ケースによっては許可制に切り替える」というハイブリッド方式をとる企業が増えています。
4. 労務管理上の注意点
副業制度を設けるにあたり、以下の点に注意が必要です
- 労働時間の通算義務(労基法38条)
- 社会保険・雇用保険の二重適用の可能性
- 情報漏洩・競業避止に関する誓約書の整備
- 労災対応(本業・副業いずれで起きたか明確化)
これらを就業規則に盛り込むことで、トラブルの未然防止につながります。
5. まとめ
副業・兼業は今や時代の流れであり、就業規則がそれに対応できていないと、企業の信頼にも関わります。
モデル就業規則を参考に、自社の実態やリスクに応じた制度設計と明文化が求められます。
労務トラブルを避けるためにも、社労士等の専門家と連携しながら、就業規則のアップデートを進めていきましょう。
※本記事は2025年6月時点の情報に基づいて執筆しています。法令・通達等の最新情報は厚生労働省サイトをご参照ください。