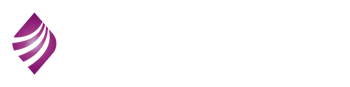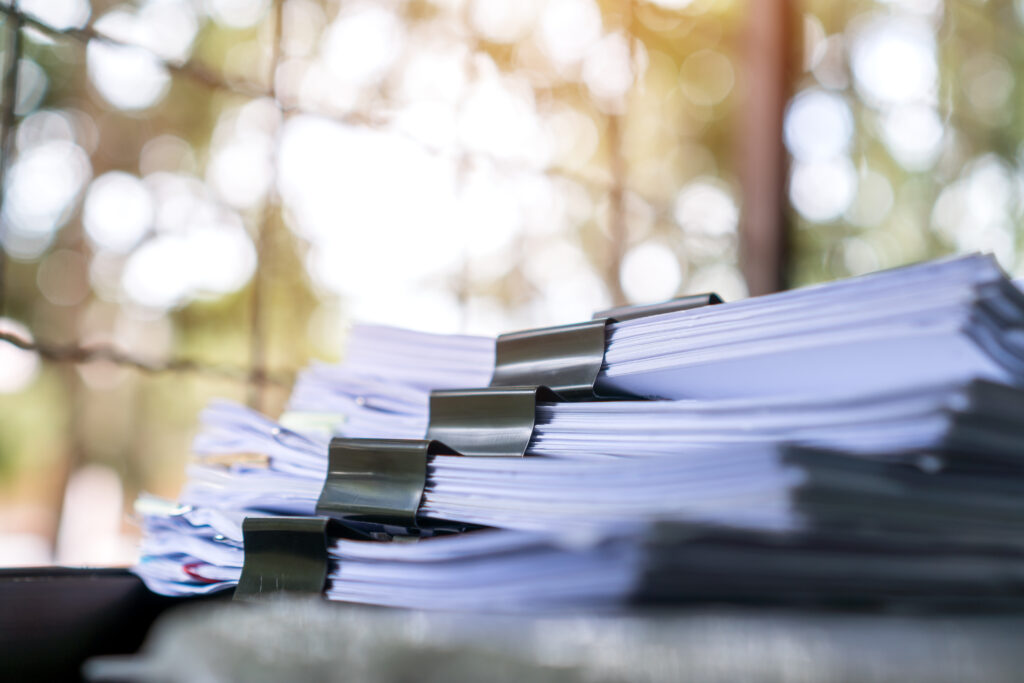
企業型確定拠出年金(DC)導入が進む中小企業:福利厚生としての活用ポイントとは?
近年、大手企業だけでなく中小企業でも「企業型確定拠出年金(企業型DC)」の導入が進んでいます。
従業員の老後資産形成支援と、福利厚生の強化を目的とした動きですが、正しく制度設計しないと逆効果になる可能性も。
本記事では、企業型DCの基礎知識から、導入時のポイント、注意すべき制度設計上の論点まで、実務に即して解説します。
1. 企業型確定拠出年金(DC)とは?
企業型DCは、企業が従業員のために掛金を拠出し、従業員が自ら運用商品を選択して老後資金を積み立てる年金制度です。
制度上、以下のような特徴があります:
- 掛金上限:月額5.5万円まで(他制度の有無による)
- 税制優遇:企業の掛金は全額損金、従業員は非課税で積立
- 運用責任:従業員自身が商品を選び、運用成績は個人ごとに異なる
個人型確定拠出年金(iDeCo)と異なり、企業が制度を用意し、一定の管理義務を持つ点に注意が必要です。
2. 中小企業が導入するメリット
中小企業にとっても企業型DCを導入するメリットは多くあります:
- 人材定着・モチベーション向上:老後資産支援による安心感の提供
- 税制メリット:企業掛金が全額損金、社会保険料の抑制効果もある
- 採用力の強化:「福利厚生がしっかりした会社」としてのアピール
特に若手社員やミドル層の将来設計への不安に対して、有効な福利厚生制度として評価されやすくなっています。
3. 導入時の選択肢と設計のポイント
導入する際は以下のような制度設計の検討が必要です:
① 掛金額の設計
- 一律支給 or 勤続年数・役職に応じた支給
- マッチング拠出(従業員が上乗せ)を導入するか
② 対象者の範囲
- 正社員のみ or 契約社員・パートも含むか
- 入社○年目以降を対象にするなどの条件設計
③ 運用教育・説明責任
- 導入時に必ず「投資教育」を行う必要がある
- 継続的な教育コンテンツの提供(外部ベンダー活用)
4. 導入までのフロー
- 制度設計の基本方針を社内で決定
- 金融機関・運営管理機関(証券・保険)と契約
- 就業規則への反映と社内説明会の実施
- 加入手続き・運用開始
実務的には社会保険労務士・金融機関・税理士との連携が重要です。
5. 注意すべき落とし穴
- 運用結果は個人責任:損失が出た場合の従業員の不満リスク
- 解約・現金化不可:原則60歳まで引き出せないため、資金繰り対策には使えない
- 管理業務の発生:加入者情報管理・投資教育義務など継続的対応が必要
まとめ
企業型DCは「福利厚生+人材定着+節税効果」を兼ね備えた制度です。
一方で、制度の運用・説明責任・従業員教育といった手間も伴うため、導入時は慎重に検討し、外部専門家と連携するのが得策です。
自社の企業文化や人員構成に合わせた設計で、将来を見据えた人材戦略を進めましょう。
※本記事は2025年7月時点の情報に基づき作成しています。制度内容・税制優遇は変更される場合がありますので、最新情報は厚生労働省・国税庁の資料をご確認ください。